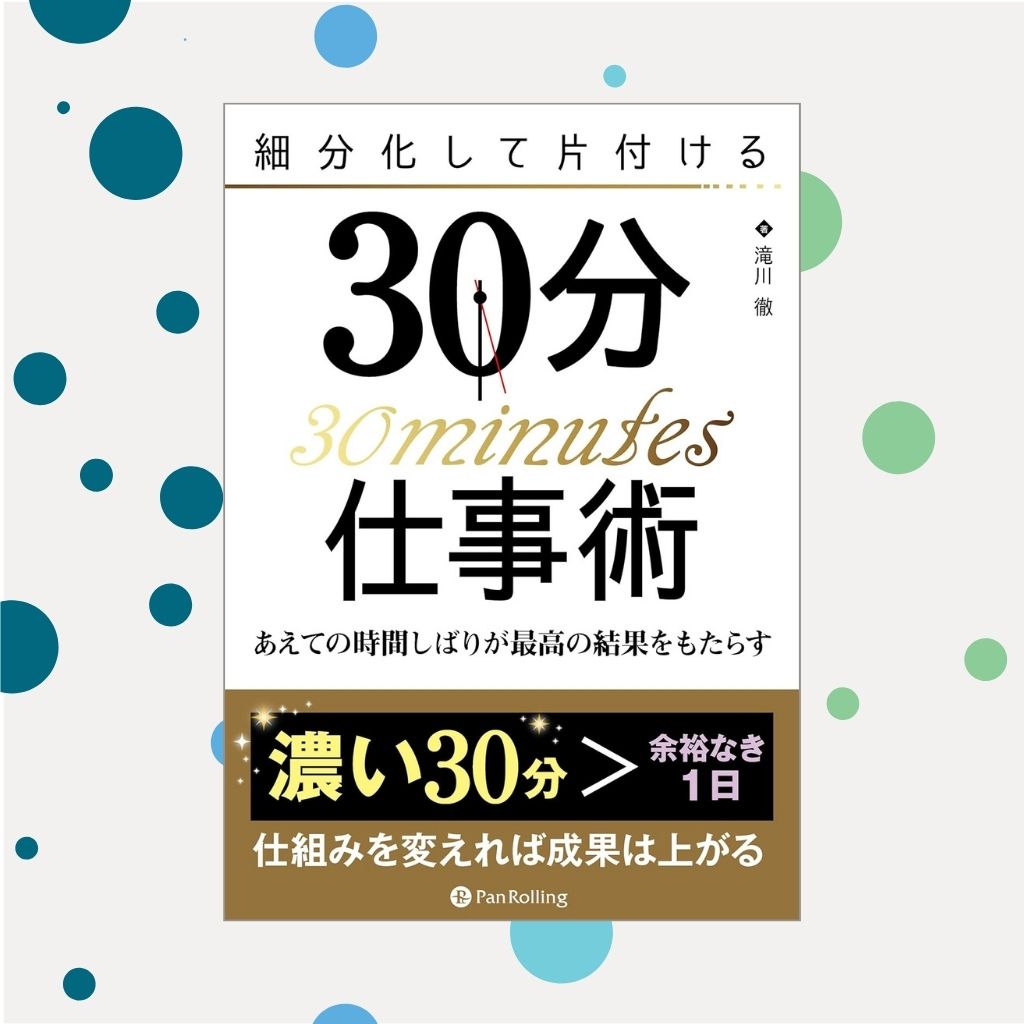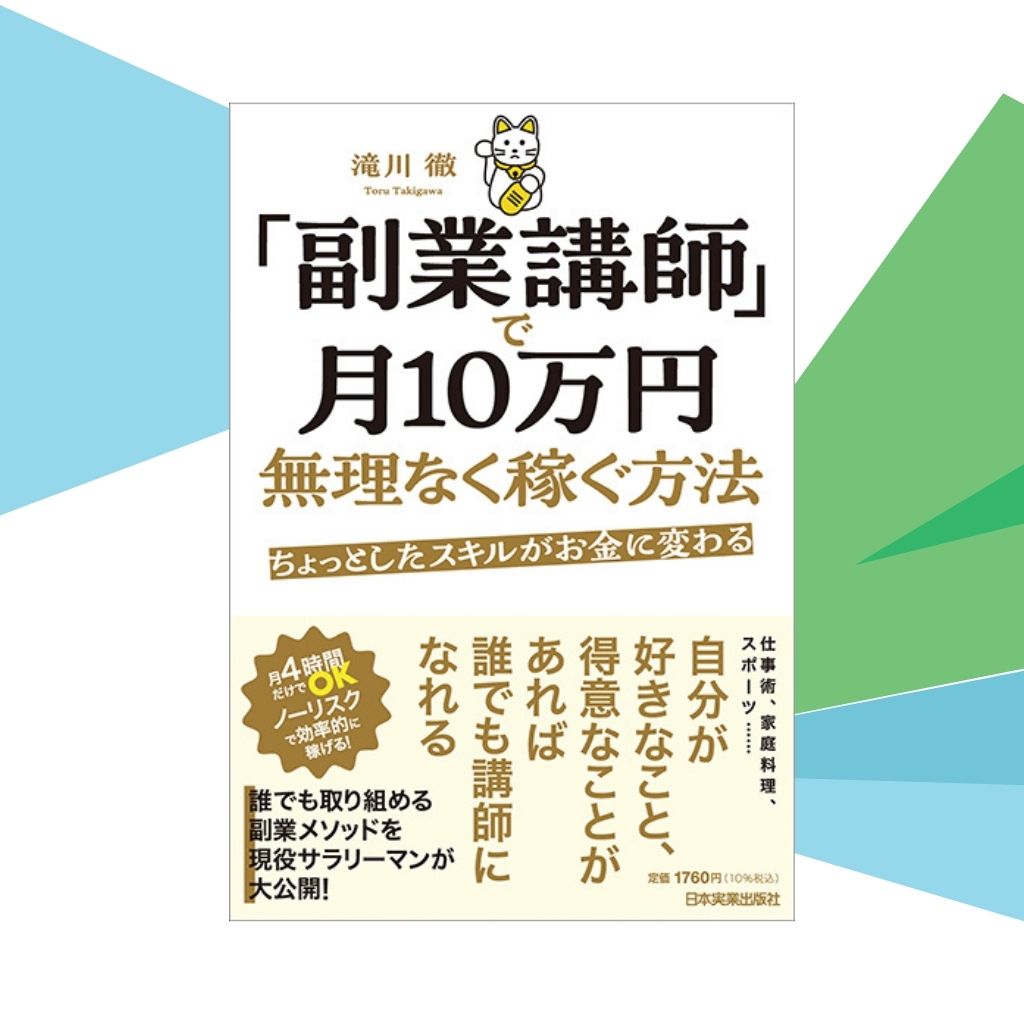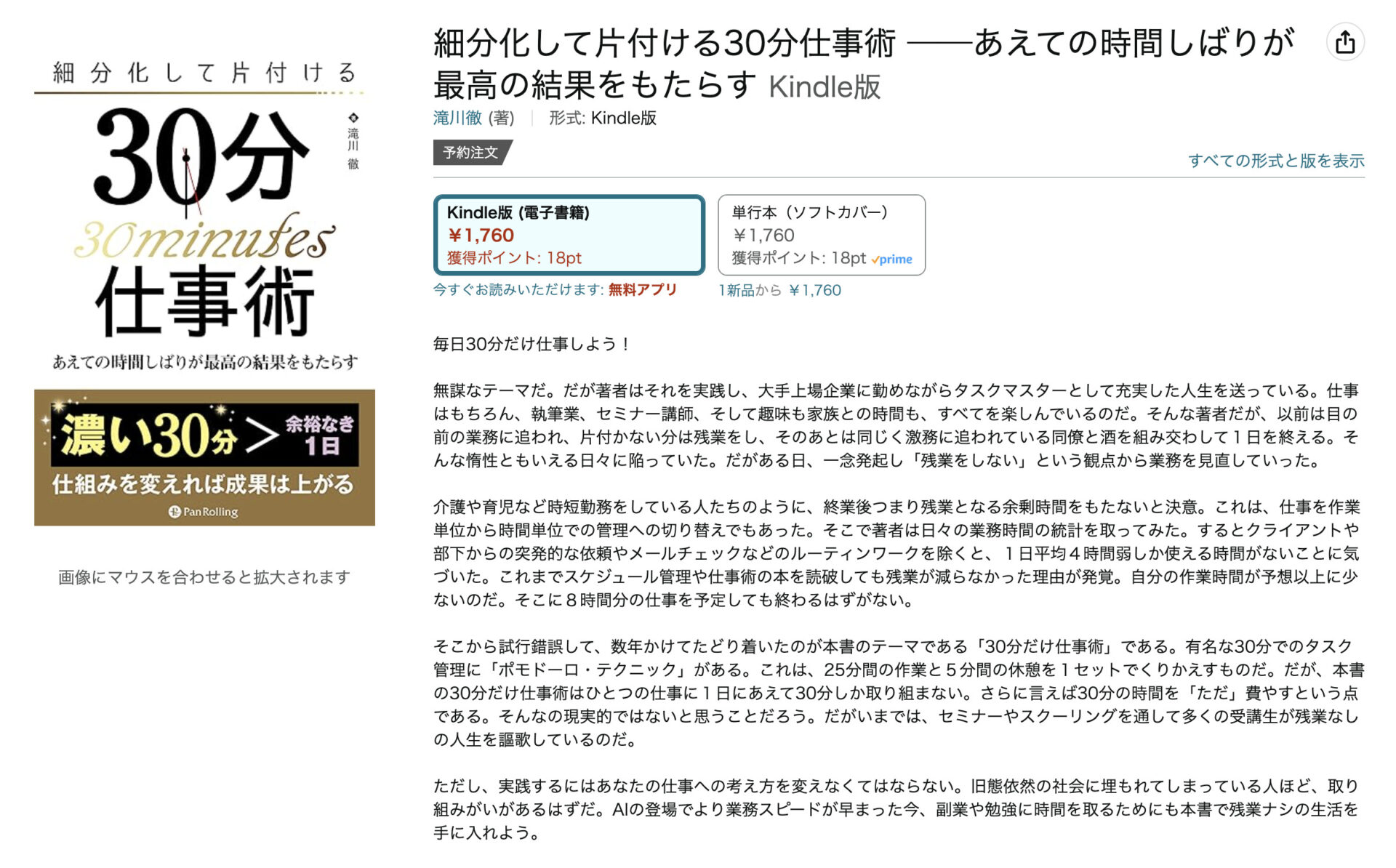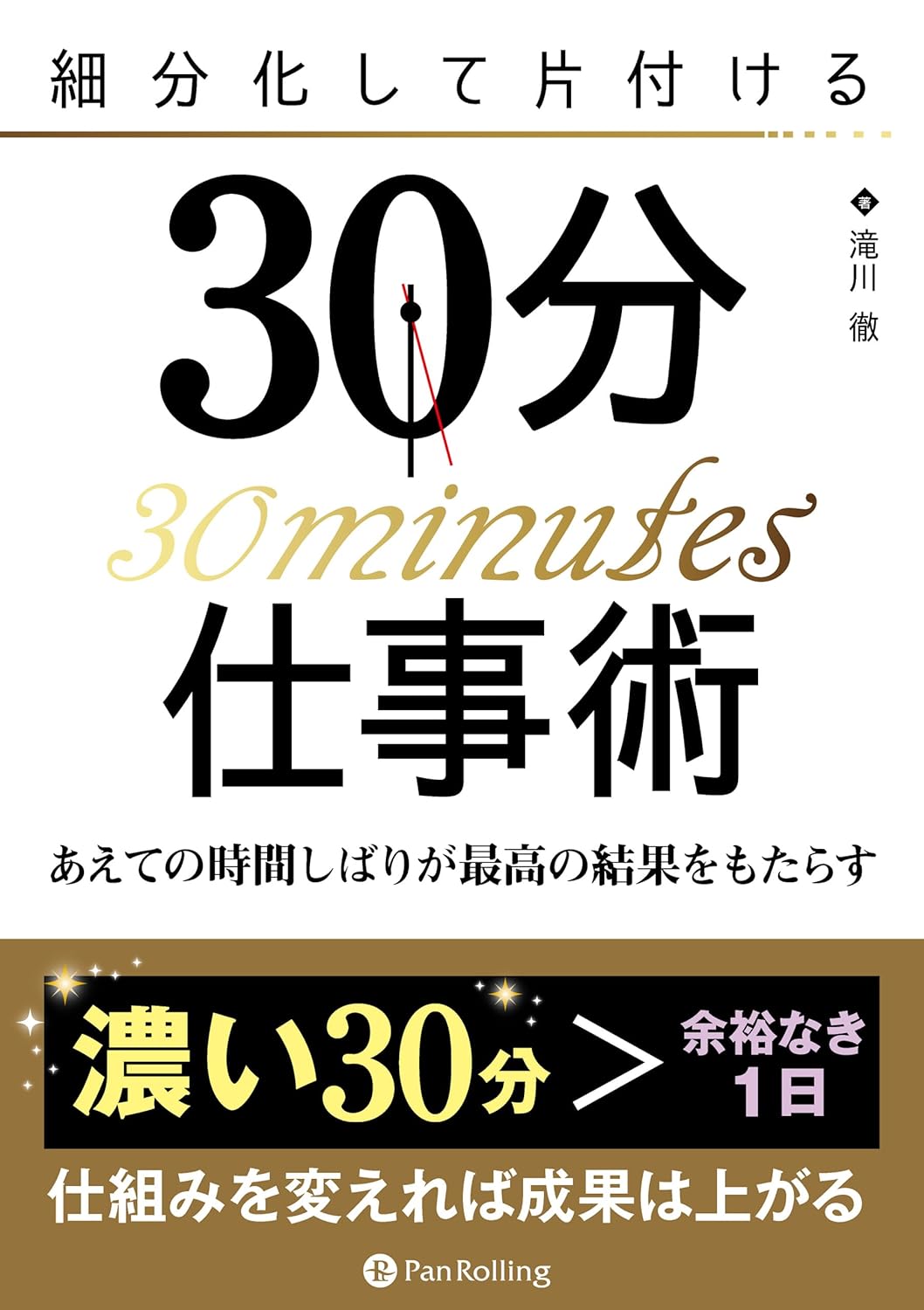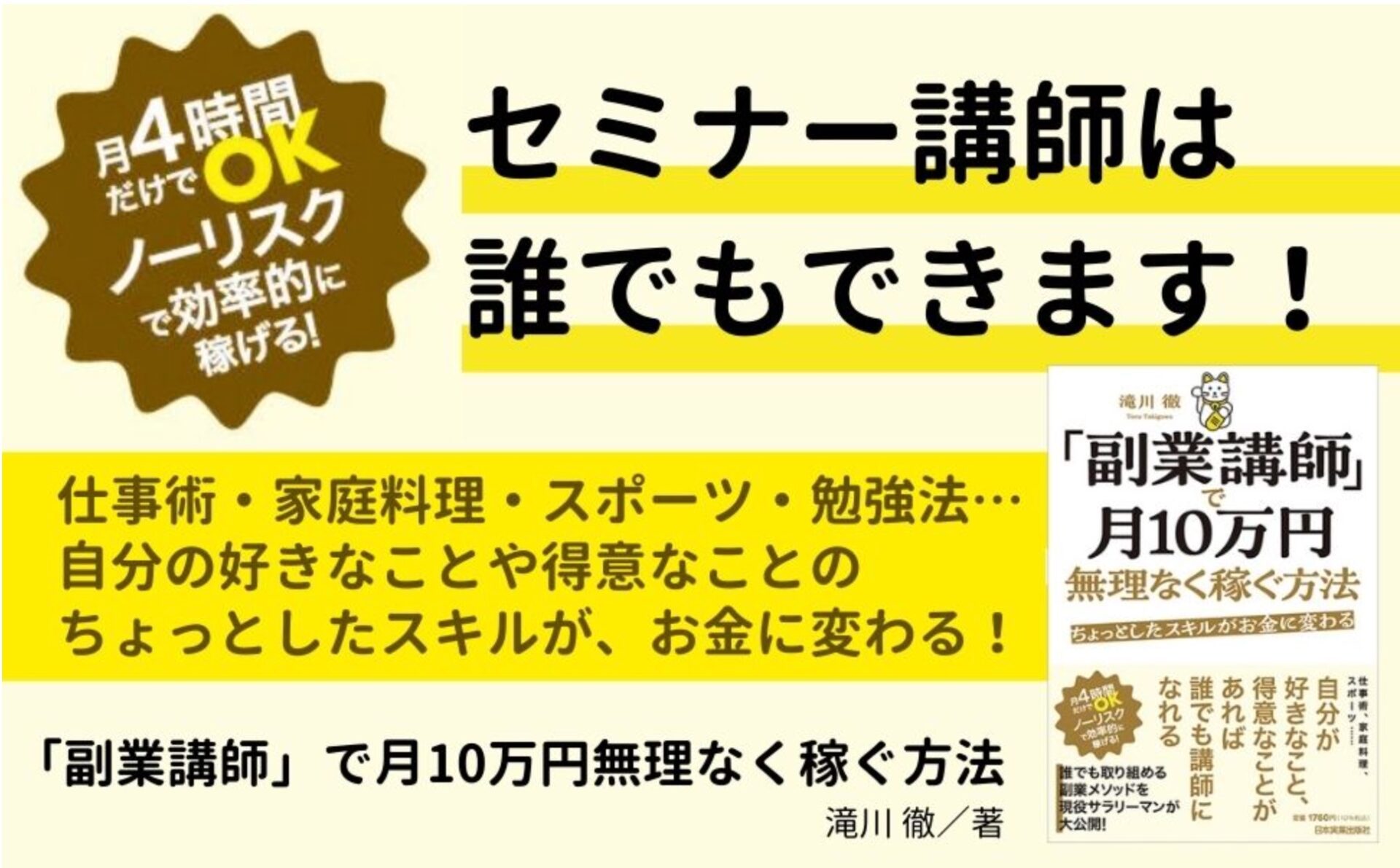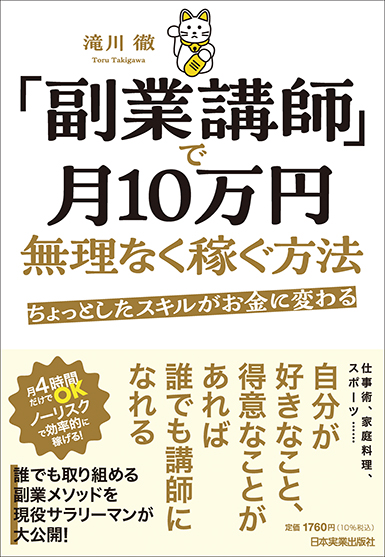タスク管理を人に教えていると、人と悩みを共有することの大切さを実感します。
先日もタスク管理の勉強会を開催しました。受講生がお互い悩んでいるところを共有することで「あぁ、みんな同じようなことで悩んでいるんだ」とか「あぁ、みんな自分と同じように苦労してるんだ」とわかります。
これが「続けること」にとても大切なガソリンになります。
広告
「自分には向いていないのではないか」という疑念が継続を断念する
なぜこれが大切かというと、人は「自分には向いてないのではないか」という疑念から継続を断念してしまう人が多いからです。
途中でタスク管理をあきらめてしまう人を見ると、タスク管理がうまくいっている講師の姿と、一見簡単なことがうまくできない今の不甲斐ない自分とを比較して「やっぱり私には向いていない」とあきらめてしまう人が多いように思います。
その講師だって昔みんなと同じように悩んできたことを無視してしまうんですね(笑)。
だからこそ、「みんな同じように悩んでいる」という事実を見ることが大切なのです。そうすることで必然的に向き不向きではなく、単に経験値の差であることが理解できるからです。
「向き不向き」はある程度継続しなければわからない
タスク管理は技術である以上、ある程度の訓練が必要なのです。一回習ったから魔法のようにすぐに効果がでるものではありません。
だから大切なことはとにかく続けること。これだけなのです。
向き不向きは確かにあります。しかしそれはある程度続けてみないと見えてこないと僕は思うのです。だからこそまず続けてみることが大切なのです。
そのためにはやはり悩みを共有できる勉強会という場が最適かもしれません。みんなとワイワイ楽しく学ぶことで、脳の中に「タスク管理を学ぶ=楽しい」という印象を刻みこめればしめたものです。
結局人は学ぶことで効果や成長を実感したり、楽しみを感じなければ続けられません。いかにその感情を自分が感じるように工夫するか。ここに習慣化のコツがあります。
僕自身も勉強会で人に教えることが楽しいと感じるからこそ、続けられるというわけです。
売り上げランキング: 2,505