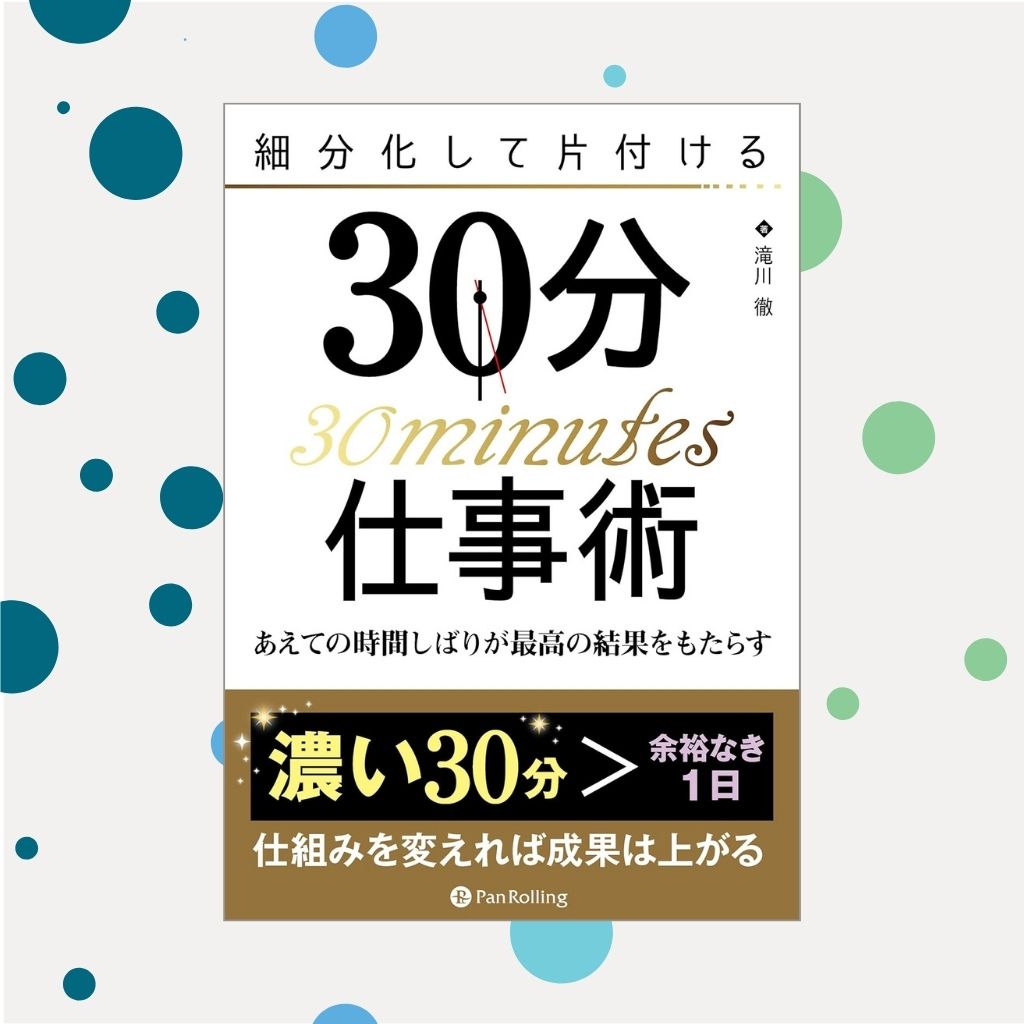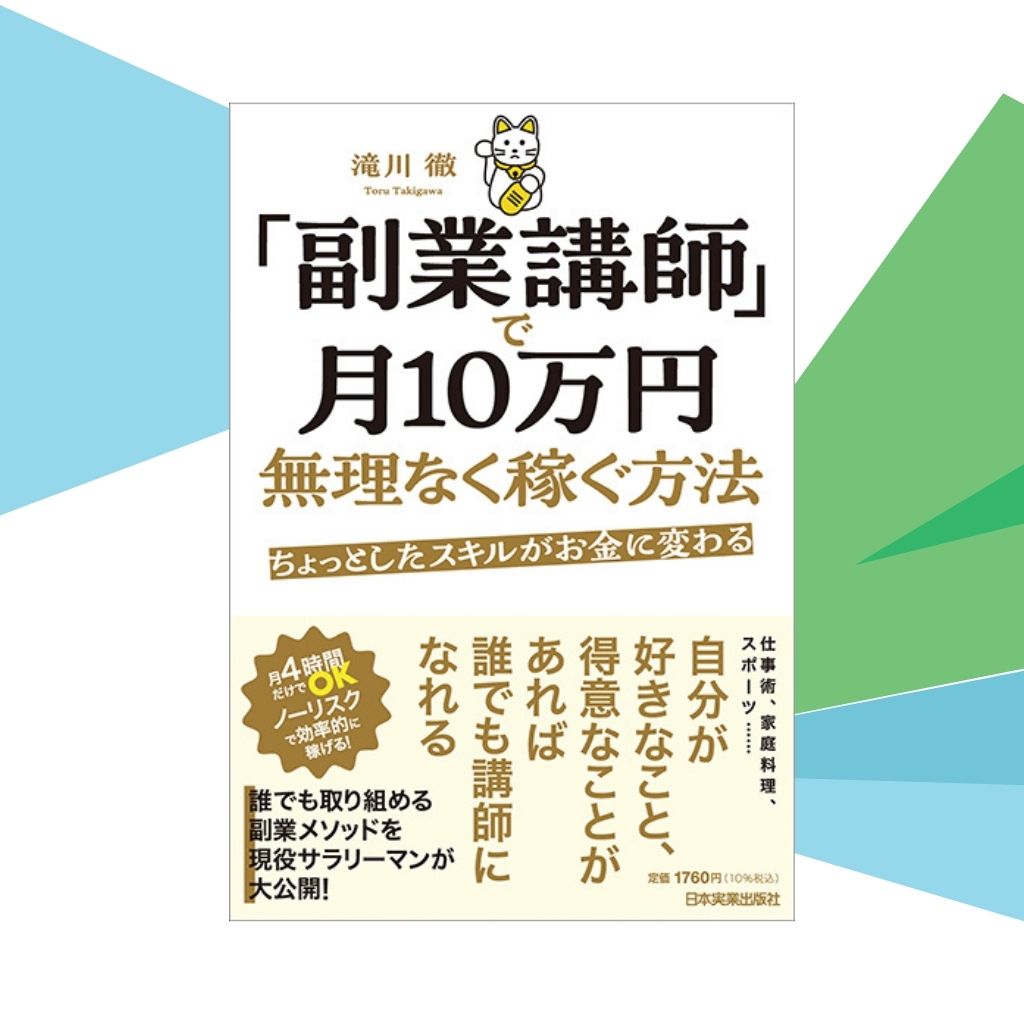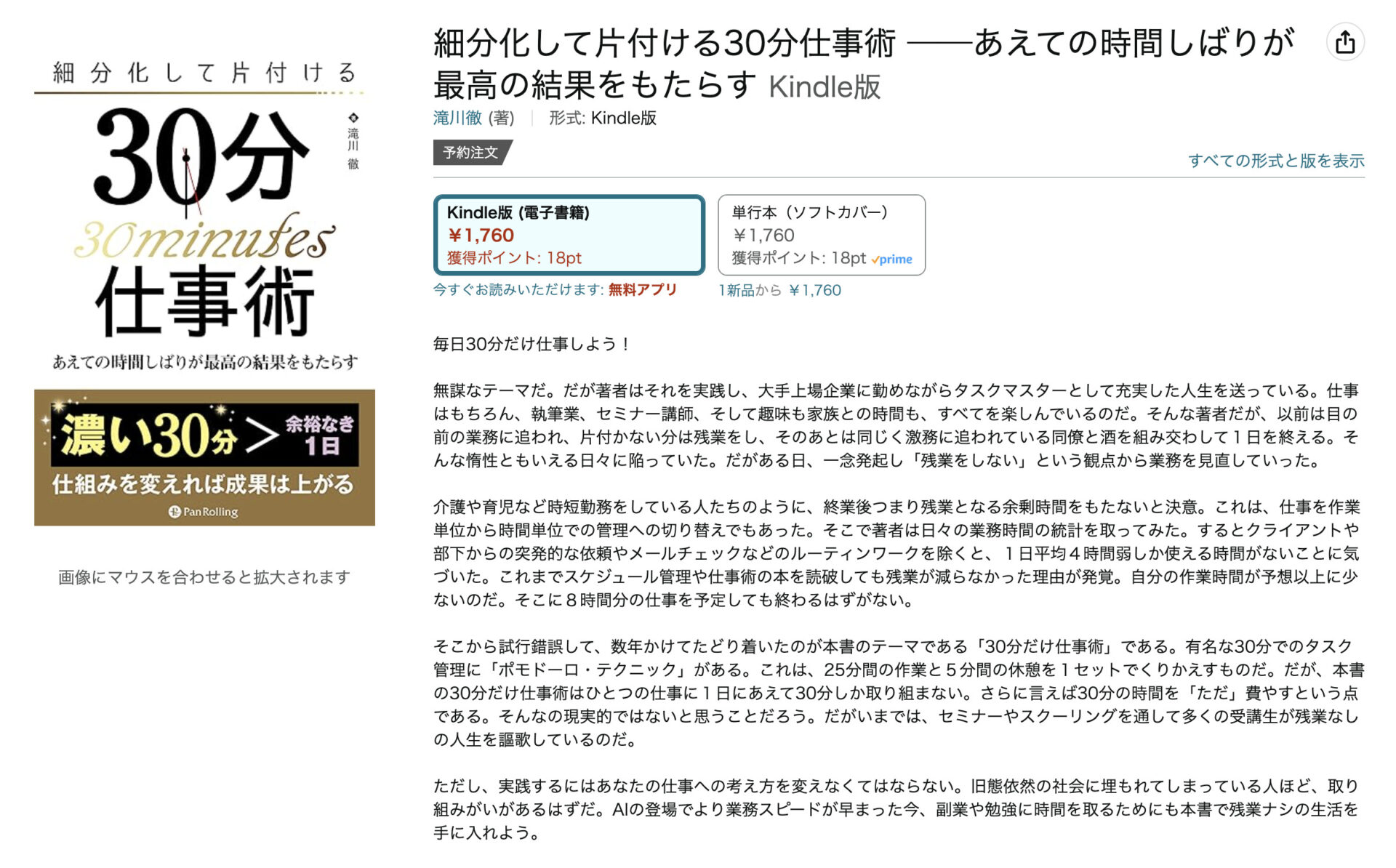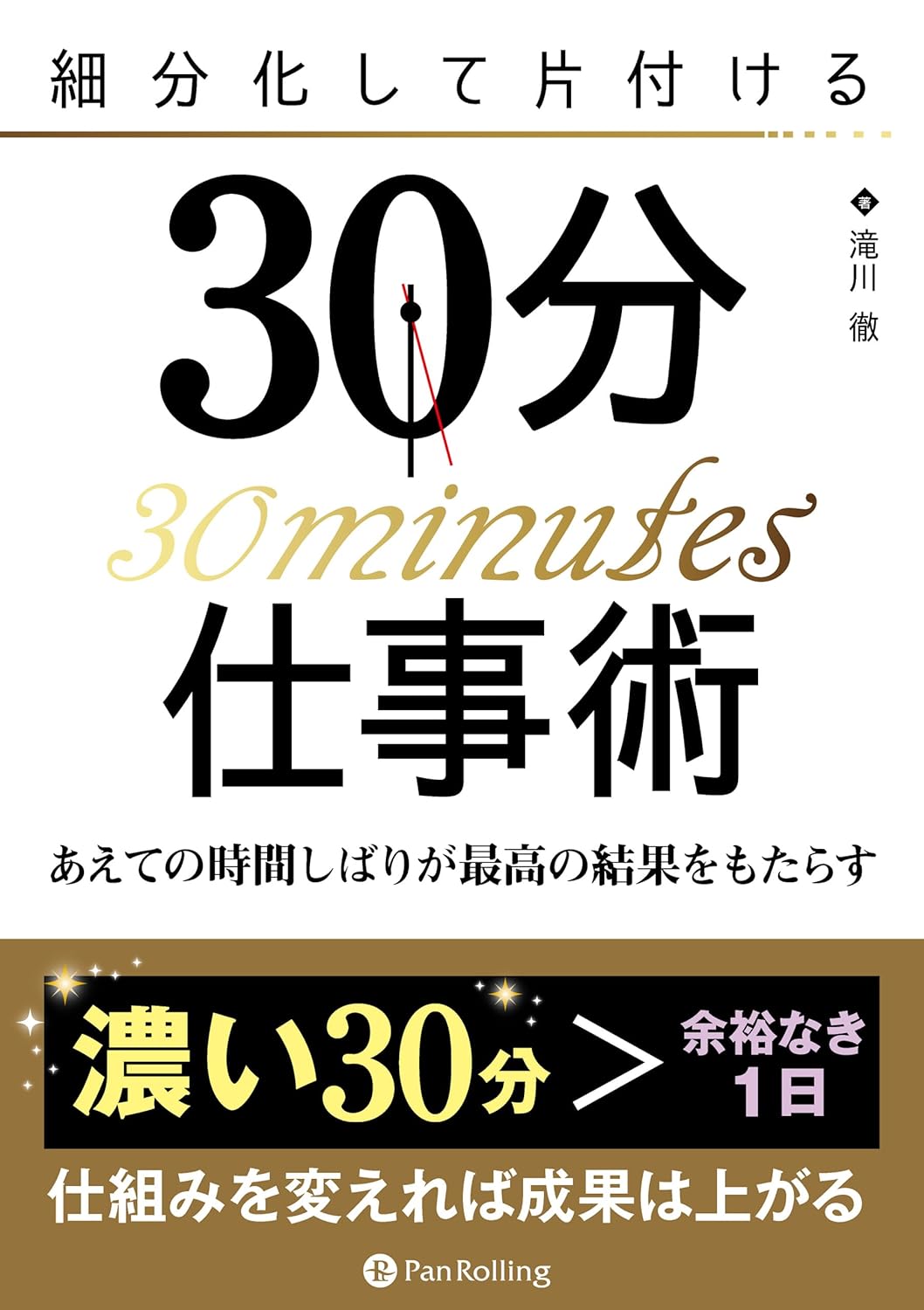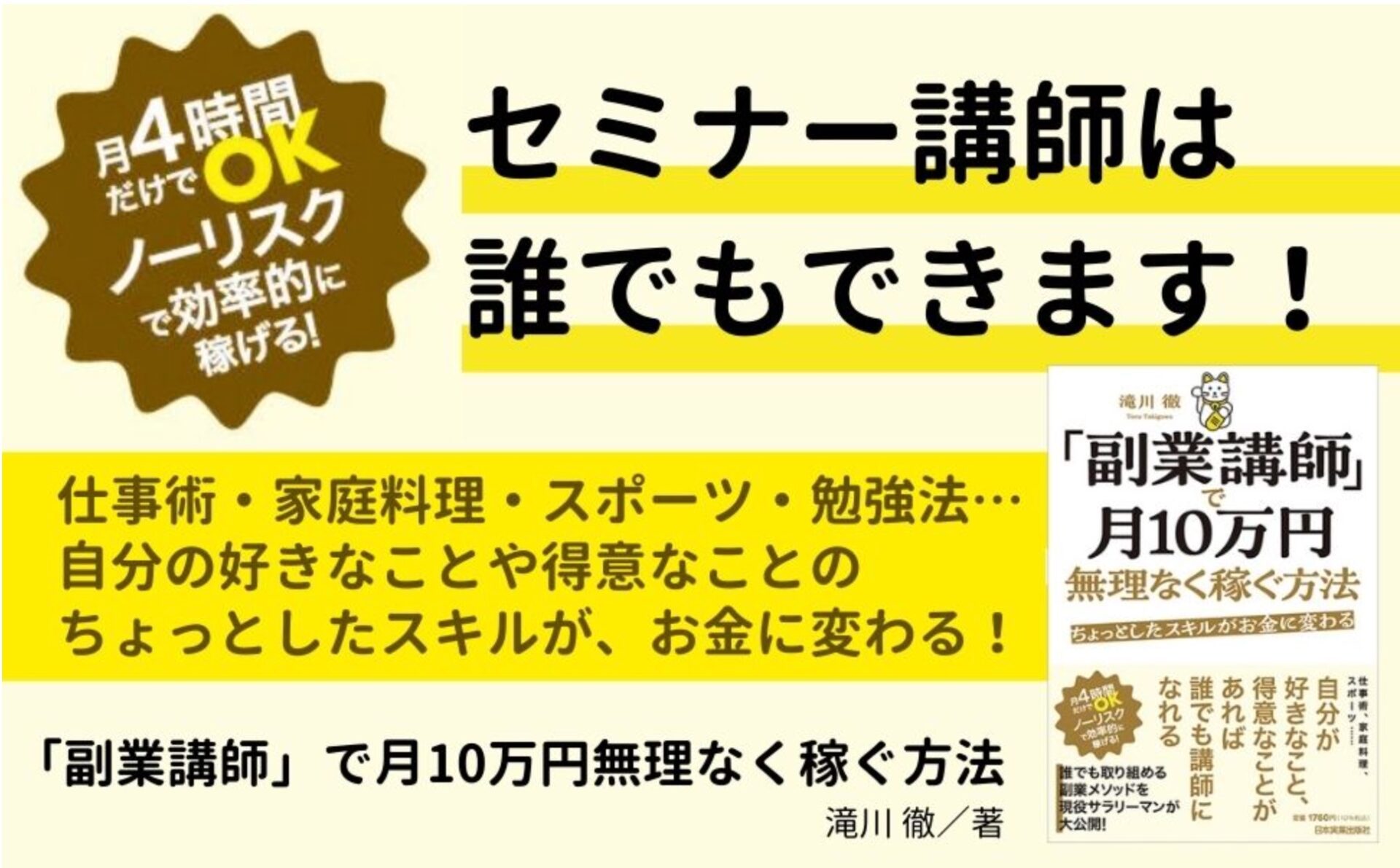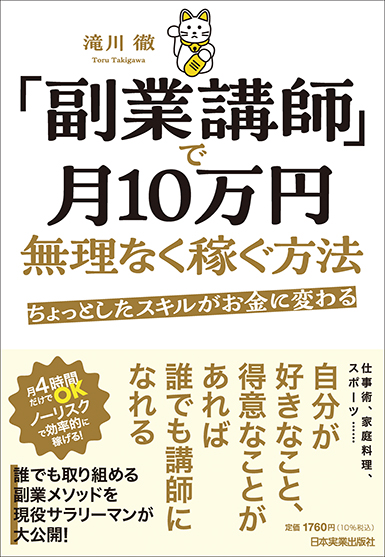ビジネス書を読んでいると、よく「リーダーは人格を磨け」と書かれていることが多いですよね。
皆さんはこの言葉をどう解釈しますか?
僕自身は20代後半にこの言葉の解釈を間違えて、とっても苦しい思いをしていたのを思い出しました。
広告
「人格を磨く」とは、人としての器を大きくしようとすること
結論から言ってしまうと、「人格を磨け」というのは「人としての器を大きくしよう」という意味だと僕は思ってます。
Being(あり方)の話だと思うのです。一方、若い頃の僕はこれをDoing(やり方)レベルで考えていました。
例をあげましょう。「人格者」から僕が連想したこと。その一つは感情的にならないことでした。
例えば職場のメンバーと議論をしていて話が平行線となる。メンバーが自分の主張を理解できないときにイライラするわけです。その時に「リーダーは感情的になってはいけない」とグッと感情を抑える。
昔の僕はこういうことをやっていました。しかし人格を磨くとは、こういう小手先のことではないと思うのです。
もっと根本的なことだと思うのです。シンプルに言えば、相手の価値観を理解しようとする姿勢だと思います。「あ、そういう考え方もありだよね」と一旦受け止める姿勢とでもいいましょうか。
人格を磨くことは、感情的になってしまうことをガマンしたり、感情を抑圧することではないと思うのです。
そういったテクニックというか、表面的なレベルを意識して行動してしまうと不自然ですよね。そうするとどこか歪みでてくるのではないかと僕は思います。
人格者という評価は「結果」である
実際に一時期、僕はうまく笑えなくなってる自分に気づきました。断定はできませんが、今思えば自分の感情や表情を不自然に抑圧していたからではないかと思っています。
人はそれぞれ考え方や価値観が違う。そのことを本当の意味で理解して、自分と違う相手の考え方を受け止めることができる人。
こういう人はそもそも感情的にならないはずです。だから結果的に人格者として評価されるのでしょう。
そういう意味では「人格者」とは、器が大きくなった「結果」だと思うのです。表面だけ整えてどうにかなる話ではありません。ガマンしてても、相手にはそのことはバレてしまいます。
「人格者であるべきだ」と思えば思うほど、人格者から遠ざかっていくわけです。だから人格者になろうとしなくていいと僕は思います。
それより自分自身がまず自由に生きて、自分自身を許可していくこと。そうすると相手の考え方や価値観を尊重できるようになる。そして結果的に人間としての器が大きくなる。
最近の僕はそんな風に考えています。さて、あなたはどう考えますか?
KADOKAWA/中経出版 (2015-09-18)
売り上げランキング: 14,854
売り上げランキング: 2,903